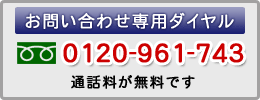共有の不動産を相続したらどうすればいい?


司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で司法書士事務所を運営しております。自宅を相続したというご相談のなかには、亡くなった親御さんとの共有というケースもあります。もちろんその場合でも相続登記をすることになりますが、その場合の注意点をご説明します。
目次
共有の不動産も相続登記をしなければならない
共有であって、単独の所有であっても、亡くなった人の権利を承継させるためには相続登記をする必要があります。登記の手続き的にはとくに違いはありません。
誰に相続させるのがいいのか。共有者以外でも良い。
父と母の共有である不動産があり、父が亡くなった場合を考えてみましょう。父の共有持分を誰に相続させるのがいのかは、よく検討しなければなりません。なお、父の相続人は、母と長男の2人であるとします。
①父の持分を母が引き継ぎ、母の単独所有にする。
②父の持分を長男が引き継ぎ、母と長男の共有にする。
この2つが考えられます。父と母の共有だったからといって、父の持分は必ず母が引き継ぐというわけではありません。通常の相続財産と同じように、相続人のなかで誰が相続するかと決めることができます。
①にするとスッキリしますね。しかし、いずれ、母が亡くなったときには、母の権利を長男に移転しなければなりません。そのときに、母が不動産の100%を持っているのと、50%を持っているのとでは税金も変わってきます。相続税も、登記の登録免許税もです。
ですので、②の方法をとり、父の持分を長男に引き継がせておけば、母が亡くなったときに、母→長男への相続はもともとの50%だけに抑えられるということになります。
しかし、相続は、税金とか手続きがどうとかよりも心情的な部分が大きく影響することがありますから、みなさんの納得する形で協議をされるのが一番だと考えます。
私道もお忘れなく
自宅が共有であれば、私道部分の権利も共有になっていることがほとんどです。私道の相続登記もしっかり行う必要があります。固定資産税が非課税になっていると、毎年の納税通知書にも載っていないことがありますから、名寄帳を確認するとか、不動産を取得したときの権利書を確認するなどしなければなりません。
相続登記を自分でやった、という方がいらっしゃいますが、私道の登記漏れなどはないのかなと心配になったりします。
私道の相続登記を忘れたまま月日がたってしまうと、いざ、自宅を売ろうとしたときに私道部分の未登記が足かせとなって、最悪は売買ができないなどということも考えられます。相続登記は放置すると、関係者が亡くなったりして登記をすることができなくなることがよくありますのでご注意ください。
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します