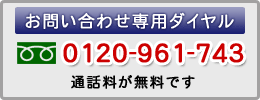やってはいけない相続放棄


司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口で司法書士を運営しております。
家庭裁判所の相続放棄手続きというものがありますが、正確な知識がないために、大変なことになってしまうケースがありますので、この記事では相続放棄の注意点についてご説明していきます。
目次
相続放棄とはなにか
自分は故人の財産について何も相続をしない、したくない、という場合に家庭裁判所に対して相続放棄の申し出をすることができます。基本的には、亡くなってから3ヶ月以内に行うべしとされていますが、例外もあります。3ヶ月を超えても相続放棄が受理されることがありますので、そのような場合はご相談ください。
相続放棄についての手続きの詳しい流れはこちらのページをご参照ください。
遺産分割協議となにが違うのか
相続人全員で、故人の財産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」とはどう違うのでしょうか。遺産分割協議はとくに家庭裁判所を通す必要はなく、相続人同士で話し合いをして遺産分割協議書を作成すればそれで足ります。遺産分割協議のなかで、「私はなにも相続しない」という人がいることがありますが、それは法律上は「相続放棄」とは呼びません。
法律上の相続放棄とは、故人の財産を一切受け取らない、その代わりに負債も全く負わない、というものです。家庭裁判所で相続放棄が認められれば、たとえば故人に対してお金を貸していた債権者から請求があったとしても、まったく応じる義務はありません。
相続放棄をするとどうなるのか
相続放棄が認められると、その人ははじめから「相続人ではなかった」ということになります。相続人とカウントされないので、遺産分割協議にも参加しないことになります。
子どもたちが全員相続放棄をすれば、次の順位の方々が相続人となりますので、故人の親が相続人となります。なお、配偶者は相続放棄をしない限りつねに相続人となります。子どもに続いて故人の親も相続放棄をすれば、故人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていればその子どもたちが相続人となります。
故人の負債を、兄弟姉妹や甥姪が引き継ぐというのも酷な話です。自分が相続放棄をしたら、次の順位の相続人となる方々にしっかり伝えて、その方々にも相続放棄を検討してもらうようにしましょう。
配偶者と子どもが相続人で子どもが相続放棄
私の事務所にお越しになるお客様のなかで、相続放棄を済ませてから、残った家族に自宅の相続登記をしてほしい、とやってこられた方がいました。
このときの相続人は配偶者と子ども2人。配偶者と子どものうちの1人が相続放棄をしていたので、もう一人の子どもが相続人となります。問題なく相続登記をすることができましたが、これがもし、子ども2人が相続放棄をして、配偶者に相続登記をしてほしい、という依頼だったとしたらどうでしょうか。
子どもたちが相続放棄をすると、上で書きましたように、故人の親または兄弟姉妹が相続人となってしまいます。子どもたちが相続人から外れる、という単純な話ではなくなってきてしまいます。
相続放棄の手続き自体をご自身で行うことはできたとしても、それによってどのような事態になるかについては、専門家の意見を聞いていただくほうがよいと考えます。
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します